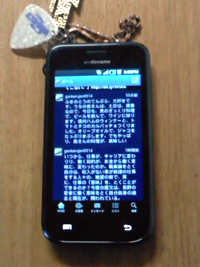- 第34回 最近、ツイッターを始めてから、一日の時間感覚が濃くなった。「日記」より簡単な「つぶやき」だとしても、言葉には文体が必要なのだと思う。さて、私のつぶやきが、どれほどに感応されるのか。
- (株)カシヨキャリア開発センター 常務取締役 松井秀夫
子どもの頃から、「独り言はいけない」といわれて育った。ぶつぶつ、つぶやく私の声を母親が聞きつけ、「いいたいことがあれば、大きな声でいいなさい」と、叱られた。
だから私にとって、つぶやくことは、自制しなければならないことの一つだったのだが、最近、つい独り言がでる。「よし、やった!」とか(最近、ありがたいことに、仕事で、何回で続いた)、「あ、痛!何で、こんなところでぶつかるの?」とか(あざが、いくつもできている)、「何で、こんなことがわからないのかな…」(一人よがりな傾向が強くなりつつあるので、気をつけなければ)とか…
人間は、どんな時、おもわずつぶやくのだろうか。最近流行のインターネット上の「つぶやき」は、アメリカ人が開発したのだから、日本人よりもアメリカ人のほうが、つぶやきに肯定的なのだろうな、と思う。「ツイッター」と名づけたオープンマイインドな発想って、多分日本人にはできないことだろう。アメリカには、コーピングというストレス対処スキルが体系化されていて、ポジティブな自問自答=意識的つぶやきが、モチベーションアップに効果的だと盛んに実践されているお国柄であることも背景にあるのだろうか?
さて、2週間ほど前から、そのツイッターを始めた。すでに、ツイッターを上手に仕事にも生かしてくれているメンバーからは、「もう、フェイスブックの時代ですよ」と、いわれた。しかし、この度の震災での使われ方にも興味があり、たとえ1回周遅れでも興味が勝ったので、恐る恐る始めたのだが、これがけっこうおもしろい。ツイッターを書いている時間が、とても濃い時間に思える。時計の秒針が、頭の中でカチカチと思考の時を刻んでいる。「これを書き終わってから、仕事」、そんな集中力がでてきた。ただ時々、他の人の、感情の残滓のような「つぶやき」に出会ってしまうと、(あまり出会いたくはないのだが)、「いいたいことがあったら、大きな声でいいなさい」と、つい、おせっかいをやいてしまいそうになる…
やはり、ツイッターにも、文体が必要なのだと思う。その人の生き様から立ち上がる思考の跡が、文体として整えられていなければならない。それが、たとえわずか140字のつぶやきだとしても、端正で読む人の心を打つ文体をつくる軌跡は必要なのだ。
好きな作家の一人高橋源一郎さんの書かれた「震災で卒業式ができなかった学生への祝辞」という、25本に分けられて発信されたツイッターを読んで、その思いが確かになった。
一つ一つは、もちろん140字の短い「つぶやき」なのだが、私の感性は、彼の骨太で上質な思想(文体)と出会い、そのボリューム以上に大きく反応していた。こういうツイッターもありなのだと感動した。たまたま同じ世代(私より2歳年下)の、同じ時代を生きてきたというフォローがあったとしても、高橋さんのツイッターは、さすが、すごい。
私も、たとえささやかではあっても、これまでの思考の跡が確かに刻まれ、言葉の一粒一粒が生き生きとつながっていく、そんな「つぶやき」を発信していきたと、願う。それができたら、「いいたいことがあるなら、大きな声でいいなさい」と叱った母親も、私の「つぶやき」を許してくれ、やがて、褒めてくれるに違いないと思うのだが…
高橋源一郎さんの「震災で卒業式ができなかった学生への祝辞」→
こちら
で読めます。
平成23年4月18日
![]()
![]() キャリアの隠れ家
キャリアの隠れ家 ![]() 第34回
最近、ツイッターを始めてから、一日の時間感覚が濃くなった。「日記」より簡単な「つぶやき」だとしても、
第34回
最近、ツイッターを始めてから、一日の時間感覚が濃くなった。「日記」より簡単な「つぶやき」だとしても、