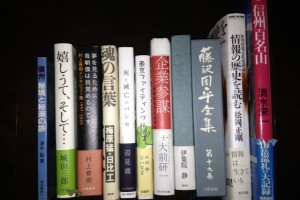
高校の同級生で、今では、長野の名門企業の役員をしている友人がいる。仕事でもお世話になっていて、節々で若いメンバーに同行しご挨拶に行くのだが、その度に、「学生の頃、松井の下宿に行くと、本箱の本が入れ替わっていて驚いた。君も、部下なんだから見習って、本をたくさん読みなさい」と、冷やかし半分に、私の代わりに読書の大切さを説いてくれている。
確かに、貧乏学生の頃、アルバイト代が入れば、新宿の紀伊国屋に行って本を買い、読み終わると、アパート近くの古本屋に売りに行った。新刊の10分の1にも満たない値段でしか引き取ってくれないが、それでも売って新刊を買う足しにした。
長野にUターンすることになり、それまでの蔵書を処分した。住まいの近くにあった吉祥寺の、金子光晴御用達の伝説の古書店によく行っていたので、引き取りにきてもらった。荷物を出来るだけ少なくするために、手元に10冊程度残してすべて処分した。軽トラック一台分にもなった。若い頃読んでいた本を、今、古書店で見つけると思わず手が出てしまい、懐かしく再読するのが、何とも言えぬ楽しみになった。
さて、長野に帰って来てからの読書は、やはり司馬遼太郎の『この国のかたち』などのエッセイ集を読んだ。歴史ものでは、古代史の古田武彦の邪馬台国シリーズにはまった。また、たまたま手にとった梅原猛の『隠された十字架』で広げられている「哲学者」「宗教家」「作家」など幾つもの顔を合わせ持った梅原猛の想像力のダイナミズムに衝撃を受け、以来40歳代の前半までは、私にとっては「梅原猛」の時代だったと言ってもいいだろう。
その後、辺見庸の『もの食う人々』と出あって、新刊が楽しみになった。彼の書く散文や詩は、徹底して冷徹に現実と向き会い、その対象と自己とのぎりぎりの戦いの発露として言葉が迸りでている、そんな文体である。そこに身を削るように刻みこまれている言葉の数々は、深い絶望の果てからしか、かすかな希望さえ生まれ得ないようにも思える。
50歳代からは、内田樹が繰り出す「内田節」に唸らされた。フランス哲学の研究者であり大学教師であり、かつ武道家でもあるという、文武両道をバックボーンに繰り広げられる社会文明論、専門分野である構造主義哲学や教育論など、縦横かつ外連味のない見識はまことに歯切れ良く、同じ年齢であることの親近感も手伝い、単純ミーハーな内田ファンになっていた。
長野に帰って来て、量として一番たくさん購入した本は、ビジネス書の類だろう。経営マネジメントやキャリア開発系の本を特にまとめ買いし、乱読した。
ある時、上司でもあり、私以上の読者家でもある先輩から、「お前は、ビジネス書ばかり読んでいるね。仕事に役立っているのか」と、からかわれたことがある。もちろん、単なる「ハウツー本」と軽んじられる内容のものもあるとは思うが、どんな本の中でも、1行は、役立つものが書かれているはずだという信念で、毎月10冊以上は、買い続け、ページをめくった。
その中でたいへん刺激になり、体系的に読み続けた著者は、アメリカの高名な経営研究者ピーター・ドラッガー、日本では、神戸大学の金井壽宏氏、コンサルタントの大前研一氏、高橋俊介氏、田坂広志氏、「編集」することの深さや読書の醍醐味を教えてくれた松岡正剛氏、ドキュメンタリー作家の柳田邦男氏。企業経営者や官僚の「志」を描いた作家の城山三郎氏などを、良く読んだ。
大好きな画家である東山魁夷画伯のエッセイ集は、その日本画に表されている静謐な自然観が言葉になって表現されていて、絵は言葉にならないイメージ、言葉は絵にならないイメージとでもいうにふさわしい表現活動であることを知らされた。
60歳近くになり、若い頃に読んだ本を再読して、同じ作品でも、初めて読んだ時のような新鮮な感動を覚えたものもあった。その作家の一人に、藤沢周平がいる。TVドラマや映画化されていて、もう一度読んで見たいと思い手にしたのだが、藤沢文学の膨大な作品群の地下に流れる共通の主題、つまり、「人間の運命にしたがい、どう『まっとう』に生きていくか」というテーマが、はっきりと見えたのだ。
例えば『海鳴り』に描かれた主人公の老境の感慨は、今になって、我がことのように沁み入る。そのエンディング。「~新兵衞は野を見た。日の下にひろがる冬枯れた野は、かつて心に描き見た老年の光景に驚くほど似ていたが、胸にしめつけて来るさびしさはなかった。むしろ野は、あるがままに満ちたりて見えた。~」
また、『蝉しぐれ』のラストシーン、お福さまが、自分の運命を振り返り、幼馴染の文四郎に絞り出すように、「文四郎さんの御子が私の子で、私の子供が文四郎さんの御子であるような道はなかったのでしょうか」という愛の告白。運命の残酷さを、これほどまでに優しい眼差しで登場人物にいわせた小説は、他にないのではないか。
身近な方が書いた愛読書では、勤務先の先代が遺した『信州百名山』がある。経営者としての厳しさと、教育者としてまた自然や音楽や絵画を愛した教養人として、本著からは、たくさんの教えをいただいた。また、筆者である清水聡さんとともに、自らもささやかに執筆のお手伝いをした『信州秘境と秘湯の旅』は、本を書くことの楽しさを体験させていただいた。長野に帰ってきてから今日までの本との関わりは、まことに豊穣の時代であったように思う。
今年も、5月の連休中、長野市内の古書店の皆さんが企画した「門前一箱古本市」に、「店主」として参加した。マルクスは、「本の虫になりたい」と願ったそうだが、私も、これからの半生は、本と共に生きて行きたいと思う。ただ、時間の制約もあるから、どんな本でもいいというのではなく、小学生から今日まで読んできた本の復習に8割ほどをあて、残りの時間は新しい本との出会いにあてるのが、ほどいいのではないか、と思っている。
平成25年5月11日
松井秀夫