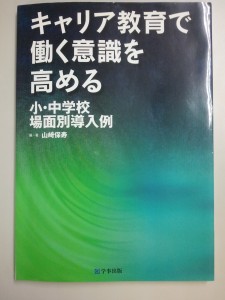 大学の就職相談員をしていて一番多い相談は、「自分らしさを生かした仕事をしたいが、どう探したらいいのかわからない」というものです。学生たちは、「自分自身らしさを生かした仕事が、必ずあるはずだ」、「そうでなければ、自分の人生は不幸になってしまう」という強迫観念にかられながら、相談室を訪れてくるようです。私は常々、そのような風潮をつくってしまったのは、大人側の責任であると考えていますので、そんな相談者が現れるたびに、申し訳ない気持が先に立ってしまいます。
大学の就職相談員をしていて一番多い相談は、「自分らしさを生かした仕事をしたいが、どう探したらいいのかわからない」というものです。学生たちは、「自分自身らしさを生かした仕事が、必ずあるはずだ」、「そうでなければ、自分の人生は不幸になってしまう」という強迫観念にかられながら、相談室を訪れてくるようです。私は常々、そのような風潮をつくってしまったのは、大人側の責任であると考えていますので、そんな相談者が現れるたびに、申し訳ない気持が先に立ってしまいます。
「自分らしさ」をあらわす言葉に、「アイデンティティ」があります。この言葉は、心理学者エリクソンが提起した概念として知られるところですが、私が初めてこの言葉に出会ったのは、1970年代後半に遡ります。アメリカ生まれの経営手法の一つとして、「CI」という考え方が日本に紹介され、経営者やマーケティング関係者に、大きな関心を呼び起こしていた頃です。
「CI」とは、「Corporate Identity」の頭文字で、「企業や組織のアイデンティティづくり」、つまり「企業の総合的なコミュニケーション活動」を表す概念として、今では広く知られるようになりました。「消費者に支持され、売り手市場をつくるために、『企業らしさ』を計画的に統一的に表現し、伝えて行くことが効果的」という主張です。
当時、私は広告業界で、コピーライターとして雑誌広告やラジオコマーシャルのコピー(広告原稿)を書く仕事に携わっていましたが、小手先のテクニック論ではなく、総合的に体系化され、理論化されたCIという考え方に、大いに触発されたものでした。
「自分らしさ」を考えるとき、私はこの「CI」という考え方を、思い起こします。企業の社会的活動の中で、多くの消費者に支持される「企業らしさ」は、企業が有するさまざまな経営資源を集中投資して、戦略的につくりあげるものです。企業と個人を同一視することはできませんが、「自分らしさ」も結局は、ポジティブに、能動的につくりあげるもの。そして、年齢とともに「変化」するものだと思うのです。
さて、「自分らしさ」について考えるとき、もう一つ思い起こすエピソードがあります。それは、今から20年前、我が子の小学生時代の授業参観でのことです。教室に入ると、前方黒板の上の壁に模造紙が貼られ、墨跡鮮やかに、「ただ、一心」と書かれていました。
それを目にして、私はCIを思い起こしました。「ああ、これはクラスを運営して行く上で、先生が子どもたちに共有してほしいアイデンティティを表したものなのだ」と、直感したのです。担任の先生が、CI理論をご存知であったかどうか、今になってはわかりませんが、まさに、「Class IdentityのCI」です。子どもたちが、勉強はもちろん、友達、部活、遊び、掃除等さまざまな学校体験や、さらに家庭に帰っての過ごし方に至るまで、「ただ、一心」の思いで取り組んでほしい、という先生の激しくも、温かさあふれるメッセージだと、深く心に染み入りました。
いろいろなものごとに対して、理屈や結果を問う前に、「ただ、一心」に取り組むことで、それまで無垢であった内面性が、少しずつ、しかし確実に「アイデンティティ」の芽になり、やがては、「自分らしさ」へと開花して行くものなのではないか。この「ただ、一心」というメッセージは、素晴らしいシンプルさと説得力を持って、「自分らしさ」づくりの本質を、示しているように思えてなりません。
「自分らしさ」にこだわり、働くことに惑い続ける若者たちの心に、30年前に発せられたこの小学校教師の「ただ、一心」のメッセージが、一体どんな風に響くのか。就職相談の機会に、一度、語り合って見たいと思います。
平成23年11月3日
※この原稿は、2006年9月、学事出版(株)から発行された『キャリア教育で働く意識を高める』(編・著 山崎保寿)に、「コラム」として掲載された私の原稿を、転載させていただきました。山崎先生(現 静岡大学教育学部教授)は、信州大学教育学部でキャリア教育を教えられていて、山崎ゼミの研究生として、私も2年間ご指導いただいたご縁で、同著に掲載していただけました。