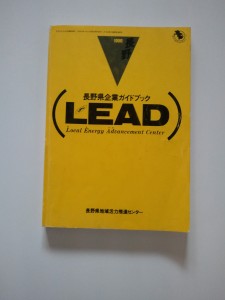
昭和60年に入社したK君と、今春、偶然26年ぶりに再開した。彼は、筋金入りの社会学部生で、彼の読書領域や社会分析の考え方に、ずいぶん刺激を受けた。
入社してすぐに私の部下になり、3年程一緒に働いた。その時ちょうど就職情報誌の原稿を書くことになっていたので、「入社1年生と配属先の上司」のとのOJTを交換日記風にまとめることにして、当時、ワープロが普及していたので、「交換フロッピー」とした。
今年彼と偶然出逢い、一緒に飲んだ時、そんなことを思い出し、掲載された当時の情報誌を引っ張り出して、読み直してみた。へえー、今でも通じる問題意識だなあ、思える内容なので、本稿として、甦らせることさせていただく。
第1回
《 私からK君へ》
(昭和61年5月)
君が、企画課に配属されて、もう1か月が過ぎた。そろそろ、会社の雰囲気にも慣れて来た頃だろう。
君の教育係ということで、これから1年間付き合うわけだが、君も見ての通り僕の仕事は、誠に多忙だ。直接顔を合わせている時間だけでは、言いたいこと教えたいことが消化不良になる場合もあると思う。そこで、この交換日記ならぬ交換フロッピーを提案した次第だ。お互い、言いたいことがあったり、じっくり話し合いたい時に、このフロッピーを、デスクの上に置いておく事にしたいと思う。思考を言葉に置き換えて行く作業は、確実にクリエイティブだから、君にとっても、僕にとっても、OJTとして、意味のあるものだと思う。
さて、今日、君が教えてくれた上野千鶴子の『私探しゲーム』『女遊び』の2冊、さっそく買って来て読んでいる。以前から名前だけは知っていたけれど、読んだのは初めてだ。『私探しゲーム』を半分程読んで、とうとう我慢できず、君と話がしたくなった。
なる程、彼女は面白い。やみつきになりそうだ。アイデンティティへの視点など、誠に新鮮に感じた。「アイデンティティを破壊する事から、アイデンティティがはじまる」というアジテーションに、団塊の世代である僕は、大変弱い。論理よりも、思い入れが先行し、ついつい深入りしてしまう。あばたもえくぼというところだ。
社会学専攻の君の、彼女に対する冷静な評価を聞かせてほしい。
《 K君から私へ》
(昭和61年5月)
Mさん、ぼくは、学生時代から上野氏のファンなので、冷静な評価ができるか心もと無いものですから、自分たちのアイデンティティについて、ぼくが考えていたことを書いて見たいと思います。
上野氏の『私探しゲーム』は、ひとまず横において、85年5月号の『Esquire』誌に載っていたDavid Leavittという若い作家の『The New Lost Generation』というエッセイから書き始めたいと思います。英文科の友人が翻訳してくれたこの、「新しい失われた世代」は、学生反乱の60年代にも、コンピュータが日常化した80年代とも隔絶した、何もない70年代に思春期を過ごしてしまったぼくらの世代を描いていました。そこにあるものは、上野氏が言う、「脱アイデンティティ」であり、浅田氏の「シラケつつノリ、ノリつつシラケル:逃走論」であり、第3舞台の鴻上氏の「すべてが幻想と知りつつ、突っ走る素晴らしさ」なのです。レイビットは、世界の終わりが近くても、決して暗くなることはない。それは、僕たちが子供の時から知っていたことだから、と書いています。
1つのムーブメントが終わりを告げた後、そして、そのムーブメントの世代だったMさんには言いづらいことですが、その世代だけに共通した体験として完結してしまい、何もかもが済んでしまった後に到着したのがぼくたちの世代だったのです。ぼくたちは、未来が決して明るいものでないことを知って(知っていると思って)います。また、アイデンティティを支えるガイドラインとなる、絶対的な価値や意味が科学(自然科学でも、社会科学でも)の分野でも疑わしいということになってきていると言うこともわかってしまっています。一つのアイデンティティにこだわるとして、そのアイデンティティの根拠となっていたパラダイムがシフトしたら、その人間は明日から何を支えに生きて行くのでしょう。
ぼくたちの世代は、新人類と言う呼び名で言われています。しかし、新人類などと言うものが存在しないことを一番よく知っているのは、ぼくたちの世代だろうと思います。一つのカテゴリーにハマルのは、そのカテゴリーと心中する事になるからです。しかし、「私は、新人類ではない」という宣言は、既に一つのアイデンティティの表現に他ならないのです。もし、新人類であることが好ましいのであれば、ぼくたちは、進んで自分たちが新人類であるというでしょう。これは、「私」というものが、相対的な判断で造られているからです。「私はここにいる」という絶対的なものではなく、「私は ○○からこれだけ離れている」と言う相対的な距離感覚がぼくたちを形づくっているのです。
これまで書いてきたことで、Mさんはどう思われたでしょうか。
常に、「私」を限定せず、相対的になることによって、時代から取り残されることがなくなったぼくたちは、そのことによって、「本当の自分」が分からなくなっているのです。
とにかく、僕たちの世代は、いくら他からの罵声を浴びせかけられても持ち上げられても、今のこの状況を生きていかなくてはならないのです。
以上 『長野県LEAD1990』(カシヨ印刷株式会社 1988年発行)より。