キャリアの隠れ家
- 第57回 中村光夫のゼミに入れず、コピーライター養成講座に通った。大学の授業料は、そちらに消えて、大学は、除籍になった。そこから、私のキャリアが始まった。
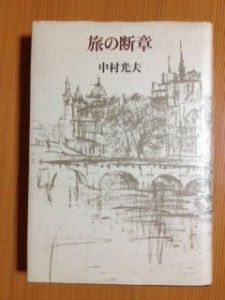
中村光夫最晩年のエッセイ集
明治大学文学部仏文科に入学して、昭和44年4月に上京した。1、2年生は、京王線の明大前で下車して4、5分の場所にある和泉キャンパスに通う。アパートは、その一つ前の駅となる代田橋に探した。確か、東京に住んでいた叔母が付き添って探してくれたように思う。
3畳一間で、家賃は3,500円。台所やトイレは共同で、もちろん、風呂などあるはずもない。それが当時は、普通の学生生活であった。キャンパスから近いところにあったので、授業が終わったあと、友人たちと、新宿か池袋へ繰り出す前の「ベースキャンプ」にもなった。
和泉キャンパスは、学生運動で、騒然としていた。一週間のうち、それでも、3、4日は、大学に行くが、授業は、休講が多く、せいぜいまともな授業は、1日1コマか2コマ程度であったように思う。授業が終わると、映画好きな仲間を誘いあって名画座巡りをするか、アルバイト先に向かった。
私は、1年生の6月から渋谷でアルバイトを始めた。確か、大信州という長野の酒蔵直営の居酒屋だった。最初は、皿洗いから始まり、簡単なおつまみなどを皿に盛るようなことも言いつかった。アルバイトを始めて2、3日してから、店長から、「冷奴」を皿に盛り付けるようにいわれた。大きな水槽から1丁ずつ素手ですくい皿に移すのだが、これが、なかなか、うまく行かない。皿に盛られた豆腐を食べることはあっても、直接手で触るなど、初めての経験である。形を潰して、店長からずいぶん叱られた。店長も長野県人だったので、同郷の好か、面倒見良くしてくれたように思う。それで、1週間ほどすると、何とか、格好はついた。私のキャリア形成のスタートは、居酒屋での冷奴の盛り付けから始まったと言ってもいいかもしれない。
授業で印象にあるのは、渋沢孝輔や大岡信などの詩人の授業であった。仏文科の履修ではなかったが、科をこえて、彼らの授業には関心があり、受講したりした。シュプレヒコールが聞こえる教室の中、この二人の授業は、大勢の学生たちが出席していて、人気があったように思う。
1年生から2年生への進級試験はあったように思うが、きちんとした試験というよりも、課題を期日内に先生に提出するといった類のもので、友人から回してもらったレポートを書き写して提出しても許されるような、ゆるいものであった。
せっかく仏文学科に入学したのだからと思い、フランス語の授業は、手を抜かず出るようにしたが、それも1週間に1、2コマ程度では、とてもフランス語で書かれた小説を翻訳できるほどの力がつけられには、ほど遠いものであった。
さて、中退であることに少々悔いを残していたので、56歳の4月から、信州大学教育学部で「キャリア教育」を学ぶ研究生となり、2年間の「学生生活」を楽しんだ。その入学手続きのため、大学時代の成績証明書が必要になり、御茶ノ水の駿河台キャンパスの文学部の窓口に行った。40年前の古めいた校舎が、高層ビルに生まれ変わり、大学のキャンパスというよりも、都心のビジネス街といった雰囲気で、驚いた。
どんな成績証明書がでてくるものだろうか、不安なまま30分ほど待っていると、「お待たせしました。ありましたよ。」といって、一通の用紙を手渡してくれた。そこには、確かに私の名前と、授業の成績が書かれていた。120単位のうち、92単位までとれていた。3年生の夏休み前までは、大学に籍があったことがわかった。
さて、中退した経過を、思い起こしたい。3年生の後期のどこかで、4年生になって受講する卒論のゼミの試験があり、当時高名な文芸評論家でもあった中村光夫のゼミの面接をうけたが、その際、「君のフランス語の成績では、僕のゼミは、無理だ」というようなことを言われ、それ以来、急激に学ぶ意欲が衰えて行った。自分は、ただ、卒業するためだけに大学にはいったわけではない。中村光夫のゼミに入れないのなら、潔くあきらめよう、そんな身勝手な理屈で、親の期待をいとも簡単に裏切った。しかし、大学に行かないのであれば、働かねばならないが、中退した学生を正規に雇ってくれそうな会社などなかった。「ものを書く仕事」をしたいと思い、シナリオライターとか新聞記者とか考えたが、その才能や学力はないと諦めた。そんなおり、映画好きの先輩から、「コピーライター」という仕事があると聞いた。そのためには、「コピーライター養成講座」(主催は、久保田宣伝研究所、今の「宣伝会議」)なるものに通うといい、と教えてもらい、銀座にあった会社に手続きに行った。
母親から送金されてきた3年生後期の授業料は、その受講料に消えた。ちょうど、大学の半期分の授業料と「コピーライター養成講座」の6ヶ月コースの授業料がほぼ同額、6万円前後だったのではないか?
講座は、夜開かれた。ほぼ毎日の講座が終わると、深夜に、都心のビルの清掃のアルバイトに行くという毎日を、半年ほど送り、修了したが、在籍中のことは、よく覚えていない。そんなに優秀な「生徒」でもなかっただろう。ただ、その講座の数期先輩に、「糸井重里という優秀な学生がいる」と、誰からとなく聞いた記憶があるのだが、今となっては、定かではない。
平成24年7月